新刊は表紙込み44ページ本になります。
本文44ページのうち、1ページは奥付です。
漫画部分は扉を入れて39ページです。
今日はあまり作業できなくて、枠線を引き終わったのが9ページ。
もう少しがんばります。
呉越春秋異聞
新刊は表紙込み44ページ本になります。
本文44ページのうち、1ページは奥付です。
漫画部分は扉を入れて39ページです。
今日はあまり作業できなくて、枠線を引き終わったのが9ページ。
もう少しがんばります。
まだ、枠線引きをやっています。
もうしばらく、かかりそうです。
Cartoonのページの表示方法を変えた方がいいかなあ…と考えています。
Twitterに投稿したものを、そのままこちらにもブログ形式で投稿していたのですが、画像もたまってきて、なんだか見づらくなってきたので。確認したら、いつのまにか200枚以上になっていました。
もう少し見やすい表示に、少しずつ変えていけたらと思っています。
原稿の合間に少しずつ作業していきたいです。
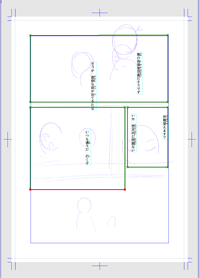
やっと全ページのコマ割りが終わりました。
といっても、コミスタの枠線定規でコマを割っただけです。
枠線はフリーハンドで引くので、この後、これをなぞって行く作業があります。
さっさと終わらせて絵にとりかかりたい!
今回はフーちゃんの話なのですが、范さんも2ページほど出てきます。
范さんは主人公ですが、ものすごく描きにくいので、こいつを先に描いてしまおうと思っています。
つづき
使大夫種因呉大宰嚭以行成。呉子將許之。
大夫種をつかわして呉の大宰嚭をつうじて和平を行おうとした。呉子はまさにこれを許そうとした。
左伝では、大夫種が和平の使者となった、そのさい呉の太宰伯嚭を通じて和平を行おうとした、ということが書かれています。
これが「越語上」では伯嚭に美女を贈った云々というのが加わってくる。
山に立てこもっていたのに美女を贈るというのはどうにも違和感を感じます。
おそらく美女を贈ったというのはあとからくっつけられたエピソードで、伯嚭を「女に目がくらんだだめなやつ」とする価値観が、後世になってだんだんできあがっていき、それにあわせて付け加えられたのではないかと思います。